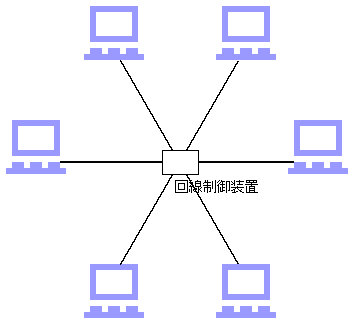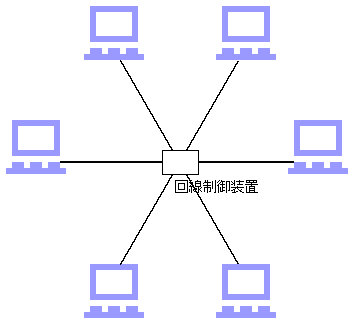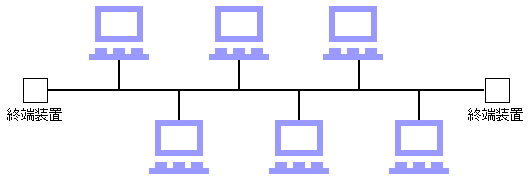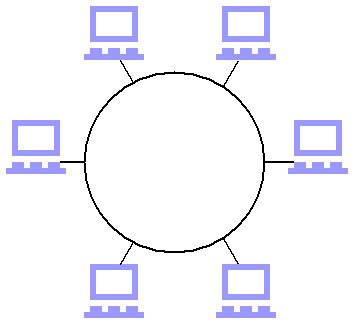2003年度前期 IT教育基礎論特論B
第11回: 情報通信とコンピュータネットワーク
■ 概要
情報通信とは何か、またどのように発展してきたかを学習する。
さらに、コンピュータネットワークの形態について学習する。
■ 目標
- 情報通信の概要を知る。
- コンピュータと情報通信技術の発達の歴史を知る。
- ネットワークトポロジーの種類を学習する。
■ 目次
情報通信とは、一般に、コンピュータ等の情報機器を通信回線で接続し、
(デジタル)信号を送受信することである。
ここでいう情報機器とは、汎用計算機やPCなどのいわゆるコンピュータだけでなく、
各種コンピュータ周辺機器、PDAや携帯電話、デジタルテレビなどを広く含めて
考えることが多い。
また通信回線も、電話線やイーサケーブル、無線など多岐にわたる。
- 1950年代以前 コンピュータの発明
-
- 1939年 アタナソフ、ベリーによるABC機械の開発
- 世界最初のコンピュータと言われる。実用化ならず。
-
- 1946年 モークリー、エッカートによるENIACの開発
- 世界最初の電子式汎用コンピュータ。
ABC機械を参考に開発されたとと言われる。
-
- 1950年代 汎用コンピュータの発展
- バッチ処理により、コンピュータ単体で使用される。
- 1956年 富士フィルム(岡崎文次)によるFUJICの完成
- 日本で最初のコンピュータ。レンズ計算等に使用。
- 1958年 東北大学(大泉充朗、野口正一)と日本電気によるSENAC-1の稼動
-
パラメトロン素子を使用した
日本で最初の浮動小数点四則演算機能を持つコンピュータ。
-
1960年代 TSS(タイムシェアリングシステム)と
コンピュータネットワークの開発
- 1つのホストコンピュータを電気的に接続された複数の端末から利用。
-
1962年 MITのLickliderによるCTSS(Compatible Time Sharing System)
の開発。
- TSSの原型。
-
1969年 米国防総省によるARPnetの開発。
-
コンピュータ同士を回線接続した現在のインターネットの原型。
カリフォルニア大学ロサンゼルス校、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、
ユタ大学、スタンフォード研究所の4台のコンピュータを接続。
-
1970年代 コンピュータネットワークの発展と
インターネットの開発
-
-
1970年 ハワイ大学のNorman AbrahamsonによるALOHAnetの開発
-
-
1973年 XEROX PARCのBob MetcalfによるEthernetの開発
-
レーザプリンタと複数のコンピュータとの接続を目的とし、
ARPnetおよびALOHAnetを参考として開発。
-
1974年 Vint Cerf、Bob KahnによるTCP/IPの提案
-
- 1980年代 インターネットの発展
-
- 1982年 ARPnetがTCP/IPを採用。
-
- 1983年 TCP/IPによるARPnet開始。
-
- 1984年 JUNET(Japan Unix Netowork)創設。
-
慶応義塾大学、東京工業大学、東京大学を電話回線によるUUCPで接続。
- 1988年 東北大学学内ネットワークTAINS完成。
-
日本の国立大学で最初の学内ネットワーク。
当時はTCP/IPではなくOSIを採用。
- 1989年 CERN(欧州素粒子物理学研究所)のTim Berners Leeによる
WWWの提案。
-
-
- 1990年代 インターネットの普及
- WWWの普及によるインターネットの一般家庭への普及が加速。
- 1990年 CERNによる世界初のwebサーバおよびwebブラウザの開発。
-
UNIXシステム上のX Window System用に開発され、
UNIXを利用する研究所や大学で急速に普及。
- 1994年 バーナーズ・リー、W3Cを設立。
-
- 1994年 Netscape社設立。
-
同年、Netscape Navigator 1.0をリリース。
- 1994年 Microsoft社がInternet Explorer 1.0をリリース。
-
- 1999年 NTTドコモがi-modeを開始。
-
コンピュータネットワークは、
コンピュータ等の複数の情報機器を相互接続した情報通信ネットワークであり、
現在のコンピュータネットワークは、
インターネットに代表されるように複数のネットワークを相互接続した
巨大なネットワークを構成するが、
その基本要素は、数台の情報機器を接続した簡単なネットワークからなる。
このコンピュータネットワークは様々な接続形態をなし、
この接続形態のことをネットワークトポロジーと呼ぶ。
代表的なネットワークトポロジーにはスター型、バス型、リング型などがある。
スター型ネットワークトポロジーでは、
中央に配置されたスイッチングハブなどの回線制御装置から
放射状に伸びた回線によりコンピュータを接続する。
接続が容易な反面、データ量が増大した場合、
回線制御装置に大きな負荷がかかる。
図1: スター型
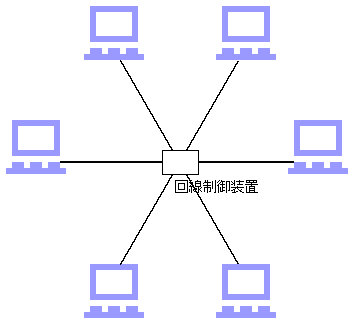 |
バス型ネットワークトポロジーでは、
一本の回線を複数のコンピュータで共有する。
安価なコストでネットワークを構築できる反面、
データ量が増大した場合、回線が混み、
十分な通信速度を得られない。
図2: バス型
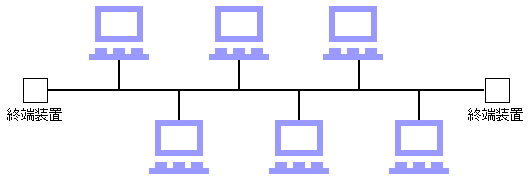 |
リング型ネットワークトポロジーは、
光ファイバケーブルを利用したFDDIなどに利用される。
バス型と同様、一本の回線を共有するが、
どこか一箇所が断線しても利用できるといったメリットがある。
図3: リング型
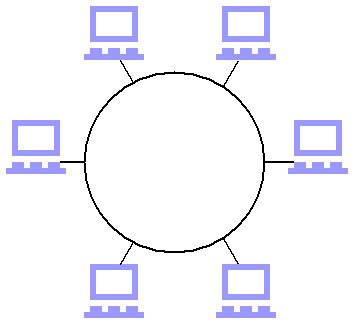 |
ネットワークに情報機器を接続したり、
ネットワーク同士を相互接続したネットワークを構築する場合、
そのためのネットワーク接続装置が必要となる。
ここでは、その主なものを挙げる。
- リピータ
-
ネットワークケーブル同士を接続するための装置。
片方のネットワークケーブルに流れてきた信号を
もう片方のネットワークケーブルに転送する。
ネットワークの延長等に使用し、経路制御は行わない。
- ハブ
-
複数のネットワークケーブルを接続し、信号を分配する装置。
一本のネットワークケーブルに流れてきた信号を
残りのネットワークケーブルに転送する。
複数の情報機器をネットワークに接続する際に使用する。
ただし、経路制御を行わないため、
通信量の多い現在は輻湊の問題があり、ほとんど利用されておらず、
替わりにスイッチ機能を有するスイッチ(スイッチングハブ)を
利用することが多い。
- ブリッジ
-
2つのネットワークを中継する装置。
一方のネットワークに流れてきた信号の転送の必要性の有無を判断し、
転送の必要性がある場合には転送を行う。
- スイッチ
-
複数のネットワークケーブルを接続し、信号を転送する装置。
一本のネットワークケーブルに流れてきた信号を
転送先に応じて回線を選択し、転送する。
回線の選択方法に応じてL2スイッチ、L3スイッチなどの種類がある。
一般に、L2スイッチの安価なものをスイッチングハブと呼ぶことが多い。
またL3スイッチはルータとも呼ばれる。
- ルータ
-
複数のネットワークを相互接続する装置。
ネットワークケーブルに流れる信号の内容に応じて、
どのネットワークに転送するかを判断し、
また、必要に応じてその信号を加工し、信号を転送する。
Last modified: Fri Jul 04 16:01:43 JST 2003